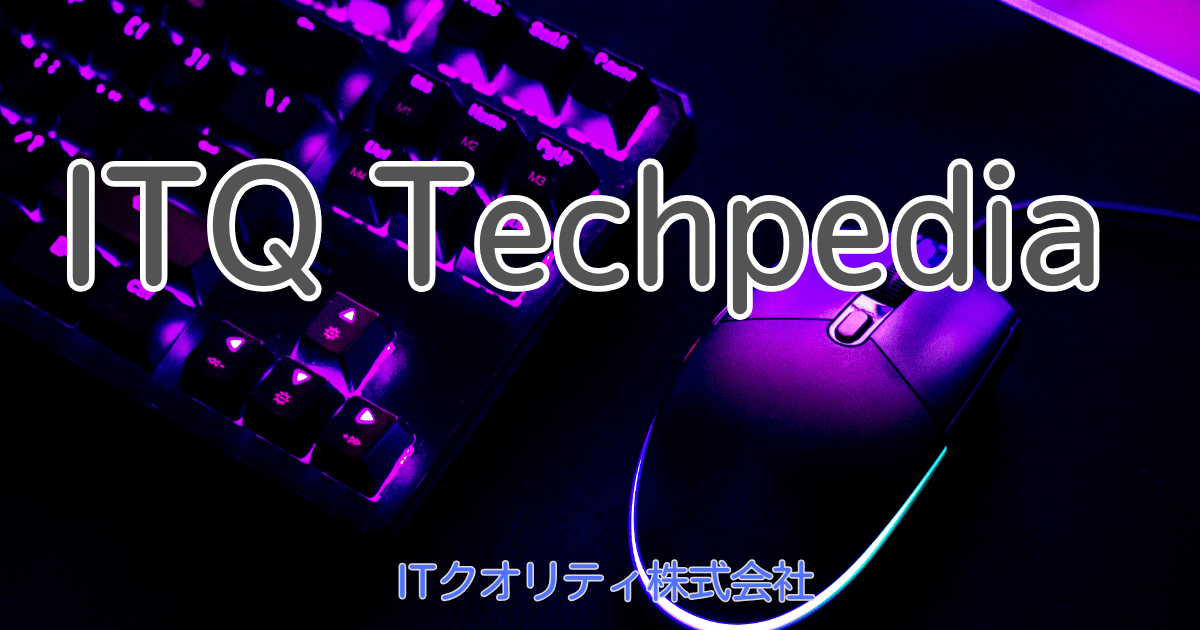1. 概要
システム化計画の立案は、情報システムの開発において最も重要な初期段階です。この段階では、企業や組織の経営戦略に基づいて、情報システムをどのように構築していくかという基本的な方向性を決定します。システム化計画は、「全体システム化計画」と「個別システム化計画」に分けられ、企業全体のIT戦略から個別のシステム開発まで体系的に進められます。
この立案過程が重要である理由は、システム開発の後工程に大きな影響を与えるためです。計画段階で目標や範囲、方針を明確にしておくことで、開発の手戻りを防ぎ、効率的かつ効果的なシステム構築が可能になります。また、経営層の承認を得るための重要な文書となるため、経営目標との整合性も求められます。
2. 詳細説明
2.1. システム化計画の立案の目的
システム化計画の立案の主な目的は以下の通りです:
- システム化の目的を明確にし、経営戦略との整合性を確保する
- 開発範囲やシステム適用範囲を明確に定義する
- 投資対効果を見積もり、経営層の意思決定を支援する
- 開発プロジェクトの基本方針や推進体制を確立する
- システム化の全体像と個別システムの関係性を整理する
2.2. システム化計画の考え方
システム化計画を立案する際には、次のような考え方が重要です:
- 経営視点の重視:経営戦略や事業目標に貢献するシステムであるか
- 業務改革との連携:単なる業務の自動化ではなく、業務プロセスの改革も視野に入れる
- システム化の基本要件:機能要件だけでなく、性能・信頼性・保守性などの非機能要件も考慮
- 段階的アプローチ:全体最適を見据えつつ、段階的な構築も検討する
- 技術動向の把握:関連する情報技術の調査を行い、最適な技術選択を行う
flowchart TD A["経営戦略・中期経営計画"] --> B["全体システム化計画 ・IT戦略 ・全社的なシステム構成 ・中長期的なシステム投資計画"] B --> C["個別システム化計画 A"] B --> D["個別システム化計画 B"] B --> E["個別システム化計画 C"] style A fill:#f0f8ff,stroke:#333,stroke-width:1px style B fill:#e6f3ff,stroke:#333,stroke-width:1px style C fill:#f9f9f9,stroke:#333,stroke-width:1px style D fill:#f9f9f9,stroke:#333,stroke-width:1px style E fill:#f9f9f9,stroke:#333,stroke-width:1px
2.3. システム化計画の立案手順
システム化計画の立案は、通常以下の手順で進められます:
flowchart LR A["1.対象業務や システムの課題 の定義"] --> B["2.対象業務や システムの 調査・分析"] B --> C["3.システム化 基本方針の策定"] C --> D["4.システム化 計画の取りまとめ"] D --> E["5.承認"] style A fill:#f9f9f9,stroke:#333,stroke-width:1px style B fill:#f9f9f9,stroke:#333,stroke-width:1px style C fill:#f9f9f9,stroke:#333,stroke-width:1px style D fill:#f9f9f9,stroke:#333,stroke-width:1px style E fill:#f9f9f9,stroke:#333,stroke-width:1px
2.3.1. 対象とする業務やシステムの課題の定義
現状の業務やシステムの問題点を洗い出し、解決すべき課題を明確に定義します。経営課題との関連付けを行い、システム化によってどのような効果が得られるかを明確にします。
2.3.2. 対象業務やシステムの調査・分析
現行の業務プロセスや既存システムの調査・分析を行います。具体的には:
- 業務フロー分析
- 情報の流れの分析
- 業務モデルの作成
- システム化機能の整理
- ユーザー要件の調査
- 関連する情報技術の調査
2.3.3. システム化基本方針の策定
調査・分析結果を基に、システム化の基本方針を策定します。この段階では:
- システム化の目的の明確化
- 開発範囲の決定
- システム適用範囲の設定
- システム方式の策定
- サービスレベルと品質に対する基本方針
- 開発スケジュール案の作成
- 概算コストの見積もり
2.3.4. システム化計画の取りまとめ
前段階で策定した内容を「システム化計画書」として文書化します。具体的には:
- プロジェクトの目的・背景
- システム化の範囲と機能概要
- システム構成案
- 開発スケジュールと工程計画
- 投資対効果の分析
- プロジェクト推進体制の定義
- プロジェクトオーナー(と実行責任者)の明確化
- リスク管理計画
| 章 | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 概要 | ・プロジェクトの目的と背景 ・システム化の目的 ・期待される効果 |
| 2 | 現状分析 | ・現行業務の課題 ・現行システムの問題点 |
| 3 | システム化の範囲 | ・業務範囲 ・システム適用範囲 ・開発範囲 |
| 4 | システム化の基本要件 | ・機能要件の概要 ・非機能要件の概要 |
| 5 | システム方式 | ・システム構成 ・ネットワーク構成 ・技術要素 |
| 6 | 開発計画 | ・開発スケジュール ・工程計画 ・概算コスト |
| 7 | 推進体制 | ・プロジェクトオーナー ・実行責任者 ・体制図 |
| 8 | リスク管理 | ・想定されるリスク ・対応策 |
表1:システム化計画書の構成例
2.3.5. 承認
取りまとめたシステム化計画書を経営層や関係部門に提示し、承認を得ます。この段階では:
- 経営層へのプレゼンテーション
- 投資決定のための審議
- 承認後の関係者への周知
- 計画実行のための体制構築
3. 応用例
3.1. 製造業でのシステム化計画の適用例
ある製造業企業では、生産管理システムの刷新を検討していました。システム化計画の立案では、まず現場の生産効率低下や在庫管理の問題点を課題として定義しました。その後、現行業務の調査・分析を行い、業務モデルの作成を通じて理想的な生産管理プロセスを設計しました。
システム化基本方針では、IoTを活用した生産設備からのリアルタイムデータ収集や、AIによる需要予測機能などを盛り込み、システム方式として、クラウドベースの拡張性の高いアーキテクチャを採用することにしました。サービスレベルと品質に対する基本方針では、24時間365日の安定稼働と、障害発生時の5分以内復旧を目標に設定しました。
プロジェクト推進体制は、製造部門の部長をプロジェクトオーナーとし、IT部門の課長を実行責任者とする体制で進めることが計画書に明記され、最終的に経営会議で承認されました。
この事例では、システム化計画の立案手順が次のように適用されました:
- 課題の定義:生産効率低下、在庫管理問題の明確化
- 調査・分析:現行業務フローの分析と業務モデル作成
- 基本方針策定:IoT・AI活用、クラウドアーキテクチャ採用決定
- 計画取りまとめ:目標SLA設定、推進体制明確化
- 承認:経営会議での投資決定
3.2. 金融機関での全体システム化計画と個別システム化計画の連携例
ある銀行では、デジタルトランスフォーメーション推進のため、全体システム化計画を策定しました。この計画では、顧客中心のデジタルサービス提供という方針のもと、5年間で段階的にシステムを刷新する長期ビジョンを描きました。
この全体システム化計画に基づき、第一フェーズとして「モバイルバンキング刷新」の個別システム化計画が立案されました。個別計画では、全体計画の方針に沿って、スマートフォンでの取引機能強化とパーソナライズされた金融サービス提供を目指し、システム適用範囲を明確に定義しました。また、セキュリティ対策やユーザビリティに関するサービスレベルと品質に対する基本方針も詳細化されました。
プロジェクトオーナーは営業企画部担当役員、実行責任者はデジタル戦略部長と明確に設定され、関連部門からの参画者も含めた推進体制が構築されました。
この銀行の例では、全体と個別の計画が以下のように連携しています:
- 全体システム化計画で「顧客中心のデジタルサービス」という大方針を設定
- 個別システム化計画では、その方針に沿った具体的な開発範囲を決定
- 全体計画の品質基準を個別計画でより詳細なサービスレベルとして具体化
- 全体計画と整合性を取りながら、個別計画ごとに最適な推進体制を構築
4. 例題
例題1
A社は、営業支援システムの刷新を検討しています。システム化計画の立案手順として、対象業務の調査・分析を行うことになりました。この段階で実施すべき主な作業として、最も適切なものはどれですか。
- システム方式の策定
- 業務モデルの作成
- プロジェクト推進体制の決定
- サービスレベルと品質に対する基本方針の策定
正解は 2. 業務モデルの作成 です。対象業務の調査・分析段階では、現行業務の流れや情報の流れを理解し、あるべき姿としての業務モデルを作成することが中心的な作業となります。1、3、4はいずれも「システム化基本方針の策定」または「システム化計画の取りまとめ」の段階で行われる作業です。
例題2
システム化計画書の内容として、以下の記述のうち誤っているものはどれですか。
- 全体システム化計画から派生した個別システム化計画では、当該システムの開発範囲を明確にする必要がある。
- システム化の目的は、経営戦略や事業目標と整合性を持つべきである。
- プロジェクト推進体制には、プロジェクトオーナーと実行責任者を明記する必要がある。
- システム化計画書は技術者向け文書であるため、経営層による承認は不要である。
正解は 4. システム化計画書は技術者向け文書であるため、経営層による承認は不要である。システム化計画書は、経営層の承認を得るための重要な文書であり、投資決定の判断材料となるものです。システム開発は多くの場合、大きな投資を伴うため、経営層による承認プロセスは不可欠です
例題3
あるメーカーで新たな在庫管理システムの構築を検討しています。システム化基本方針の策定段階で検討すべき項目として、適切でないものはどれですか。
- 関連する情報技術の調査
- システム適用範囲の設定
- システム化機能の整理
- プログラムの詳細設計
正解は 4. プログラムの詳細設計 です。プログラムの詳細設計は、システム開発工程の中で行われるもので、システム化計画の立案段階では行いません。システム化基本方針の策定段階では、システムの全体像や基本的な方向性を定めることが目的であり、1〜3の項目が検討対象となります。
例題4
B社では、業務効率化のためのシステム化計画を立案中です。以下の記述のうち、システム化計画の立案における考え方として最も適切でないものはどれですか。
- 経営戦略との整合性を確保するため、システム化の目的を明確にした。
- 投資対効果を重視し、現状の業務プロセスをそのまま自動化することを基本方針とした。
- 全体システム化計画と個別システム化計画の関係性を明確にした。
- サービスレベルと品質に対する基本方針を策定し、非機能要件も考慮した。
正解は 2. 投資対効果を重視し、現状の業務プロセスをそのまま自動化することを基本方針とした。システム化計画の立案では、単に現状業務を自動化するのではなく、業務改革の視点も含めて検討することが重要です。現状業務をそのまま自動化すると、非効率なプロセスも含めてシステム化することになり、真の効率化につながらない可能性があります。適切なシステム化計画では、業務プロセスの見直しと最適化も含めて検討する必要があります。
5. まとめ
システム化計画の立案は、情報システム開発の最初のステップであり、その後の開発プロセス全体の成否を左右する重要な段階です。立案の目的は、経営戦略に沿ったシステム化の方向性を定め、開発範囲やシステム適用範囲を明確にすることです。
立案手順としては、①対象とする業務やシステムの課題の定義、②対象業務やシステムの調査・分析、③システム化基本方針の策定、④システム化計画の取りまとめ、⑤承認の5つのステップが基本となります。
全体システム化計画では企業全体のIT戦略を描き、それを基に個別システム化計画でより具体的な開発計画を立案します。計画書には、システム化の目的、開発範囲、システム方式、サービスレベルと品質に対する基本方針、プロジェクト推進体制、プロジェクトオーナーと実行責任者など、必要な要素を漏れなく記載することが重要です。
最終的に、システム化計画は経営層の承認を得ることで正式に発動し、その後の開発プロジェクトの指針となります。計画段階での綿密な検討が、システム開発の品質向上とコスト削減に大きく貢献することを忘れてはなりません。